先の参議院選挙に出馬し、落選という結果に終わった神田敏晶氏。神田氏と言えばビデオ/ITジャーナリストとして、パソコン雑誌やIT系ウェブサイトに数多く寄稿してきた人物だ。彼は選挙中に何を感じ、この選挙で何を変えようとしたのだろう? 本人の言葉で本音をぶつけてもらった。
今回の選挙でインターネットはどこまで使えるようになったのか?
“自民大敗、民主大勝”という今回の選挙の結果で、参議院の議席では野党が大きく“与党化”する結果となった。今後は、民主党の采配が試される時代でもある。政治の新しいドラマが展開し、新閣僚の発表や、衆議院選挙など、政治世界のカードとポストは大きく大きく変わろうとしている。
7月末に行なわれた参議院選挙にボクは、ひょんな理由で出馬することとなった。「今回の選挙でインターネットはどこまで使えるようになったのか? そしてインターネットだけで戦う選挙で、何票くらい獲得できるのだろうか?」──そんな疑問を感じたからだ。
国会の“茶番劇”をネットで伝えたかった
ボクが選挙に出たきっかけをもう少し話しておこう。
6月30日、内閣不信任案が民主党から出され、ボクは、その内容を国会で傍聴することにした。国会の傍聴は、衆議院は911の米テロ以降、議員の紹介がないと不可能となっているが、参議院は可能だ(衆議院の傍聴、参議院の傍聴)。衆参で、なぜこうも違いが出るのかは疑問である。
実際に衆議院を傍聴して思ったことだが、野党が今回の“内閣不信任案”を提出したところで、絶対多数の与党側(票差200)が否決とすることは明確だった。
野党側の本当の趣旨は、参議院を控えたこの時期に、マスメディアを通じて世論にアピールするというところにあったのだろう。たとえ否決されたとしても、マスコミは野党が不信任案を提出したということをニュースにする意味があるからだ。
しかし国会としては、提出された案についてシステムで対応するから、会議を開催しなければならない。通らない案を発表する野党、通らない案をヤジる与党。
しかも国会の中では、多数のヤジが飛び、テレビの映らない後ろのベテラン議員席(前方は新人が座る)では、ダベるもの、席をウロウロするもの、後ろの席と雑談するもの、眠り続けるものまでいる。これじゃあまるで、荒れた中学校のクラスそのものだ。いやそれ以上に悲惨な状態である。この人たちに日本を任せていて本当に大丈夫なのだろうか? という疑問まで抱いた。
ボクはこの時、この国会の“茶番劇”を、もっと国民に伝える努力をしたいと感じた。そして出馬を決意したのだ。
マスメディアに向けてではなく、インターネットを通じてもっと国会の中身を“見える化”する必要がある。パフォーマンスや“どぶ板選挙”という世のため人のためには全然ならない選挙活動に費やされるパワーを、もっと議論すべきところへと向けるべきだと感じたのだ。
毎日かかる1億8720万円もの人件費
政治に無関心な人も多いと思うが、税金を毎月強制的に搾取されているサラリーマンはもっと使われ方を気にするべきだと思う。
例えば、先に述べたような国会運営に対して、なんと1日あたり約1億8720万円もの歳費(しかも人件費だけで)が投入されている事実には愕然としてしまう。
1日あたり約1億3000万円
政治資金は一議員あたり26万6000円×480名(衆議院)なので、人件費だけで1億2480万円。参議院(240名)を合わせると、1億8720万円もの人件費になる。26万6000円の内訳は、月給200万円(期末手当含む)+通信費100万円+公設秘書3人分166万円+立法調査費65万円÷20日だ。
政治資金は非課税で、もちろんこれらの費用には1円も税金がかからないため、使い勝手としては2倍と考えてもいいだろう。すると毎日、3億7440万円もの価値が投入されていることになる。まるで、毎日国会に、三億円事件の犯人が集団でうごめいているように見えてくる(笑)。
しかもときには、“禁足”というルールによって、議員が本会議(議員全員で構成される会議)の場から5分以内の場所に幽閉されたりするから、さらにムダな使われ方となってしまっている。禁足については、馳浩議員の“永田町日記”を参考にしてほしい。
(次ページに続く)






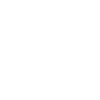 お気に入り
お気に入り














































