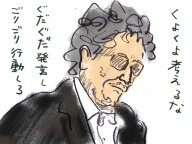非実在青少年。
どういう意味だろう。
「不在地主みたいなものか?」
「むしろ無産階級かと。不在小作人。でなければ透明労働者?」
「前衛気取りのたわごとだろ。可塑的必然性みたいな。70年代に流行した思わせぶりのパラドックス。それだけの話さ」
「ズバリ" Nowhere man "だな。ビートルズの歌にある。邦題は「ひとりぼっちのあいつ」。イエローサブマリンの主人公にして自失したインテリの象徴。具体的にはナリのデカい迷子ってとこかな」
「不登校の言い換えかもしれないぞ」
「素直に読めば無戸籍児童の成れの果てだろ。無戸籍で無国籍な法令上のブラックホール。人権のエアポケット。哀れな……」
「違うね。正反対。非実在青少年は、子ども手当受給のために近未来の悪党が捏造する実体を伴わない戸籍だよ。戸籍上だけ存在する幻の扶養家族。クニに置いてきたとか言って、山ほど申請者があらわれると思うね」
「普通に虚無的な若者の自分語りだよ」
「確かに、虚無的な連中に限って自分が大好きだったりするからな。で、私は実在しないだとかなんだとか、そういうポエムを書くわけだよ。ぐだぐだと」
「で、永遠に自分探しをするわけだ」
「名刺の住所が『旅行中』だったり」
「永遠のジャック&ベティ」
「おお、ジャック・ジョーンズ。懐かしい」
「『ぼくは少年ですか?』という奇妙な質問をいまだに繰り返しているんだろうか?」
「ぼくは不在ですか、ってか?」
結局、「非実在青少年」は、字面だけでイメージを確定できる言葉ではない。
あまりにも意味不明。というよりも、多義的過ぎて着地できない。
調べてみると、これは、東京都がこの3月に都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案の中に出て来た言葉で、その意味するところは、「漫画やアニメに登場する18歳未満のキャラクター」らしい。30日に本会議で採決され、可決されれば10月から施行となる。原文は以下の通り。
「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に関わる非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるもの」(「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」第七条の改定案より。第七条は「不健全な図書等の販売等の規制」を扱う箇所。改正前の同条例はこちらから)
条例の改定案は、児童ポルノを規制する内容を含んでいるものなのだが、その施行にあたって提案者側は、「実在していなくても、全体として青少年(18歳未満)の特徴を備えたキャラクター」、すなわち、「非実在青少年」を性の対象として描写することを禁じなければ、実効ある規制にはならない、と考えたわけだ。
萌えイラストやCGの少女が性行為をする、みたいな作品は、たとえ現実の子供が被害者になっていなくても、その作品を見ることになる青少年の健全な育成にとって有害であるがゆえに規制せねばならない、と。
規制推進派の見解から私が読みとった限りによれば、現行の法律でマンガやアニメに網をかけるのは難しいらしい。なんとなれば、架空のキャラクターには「被害者」が実在しないから。さらに、架空のキャラクターは児童ポルノ法で取り締まる際の構成要件である「18歳未満」と特定することも難しい。作品の中ならばどうみても学童年齢の少女に
「私は175歳です」
と言わせることもできるから。そこで作中の設定はどうあれ「見た目が18歳未満ならば、取り締まりの対象にできる」ということにした。
なるほど。
つまり彼らは、萌えイラストを法の網にかけるために、新しい概念を発明したのだね。
非実在青少年。なんというバーチャルリアリティな情熱。
もっとも、条例案は、実在しない青少年の人権を守ろうとしているのではない。いくらなんでもそこまでブッ飛んではいない。むしろ、バーチャルなキャラクターを仕立てたおとり捜査に近い(なお誤解がないように言っておくが、もちろん問題は「性交又は性交類似行為に関わる」描写にあるわけで、普通に非実在青少年のイラストを描いただけで条例違反というわけではない。うむ、今回のイラストは明らかにおとりだった。すまない)。
* * *
21世紀の文明国は、各種の「変態」的な性描写について、寛大に構える傾向にある。
つまり、「どんな種類の性的偏向であれ、同好の士が閉じたサークルの裡で楽しんでいる限りにおいて、お上は、あえて規制には踏み込まない」というのが現代的な流れだということだ。サディズム、マゾヒズム、同性愛、各種フェティシズム、あるいは、「○○専」という言い方で分類される畸形的な倒錯傾向であっても、表通りに出て来ないのであれば黙認される。勝手にしろ、と。
別の見方をするなら、自らの性的嗜好のうちに何らかの逸脱傾向を内在させている人々は、意外なほど数が多いということなのかもしれない。となると規制なんか不可能だぞ、と。さらに踏み込んだ言い方をするなら、「変態」についての問題は、「欲望の分野に『普通』なんてものが存在するのか?」という非常に厄介な問いを含んでいるわけだ。
あるのだろうか?
私は答えを持っていない。というよりも、私の「普通」が、世間の「普通」とどんなふうに違っているのかについて述べることが、そもそも「普通」ではないということだね。
語ること自体、変態ですよ。
児童ポルノは話が別だ。これについてはどこの文明国でも特殊な扱いになっている。というのも、児童ポルノが対象としている性的なターゲットは、「同好の士」ではなくて、われわれの子供たちだからだ。
当然、話はSMクラブや出会い系におけるあれこれとはまったく違う展開になる。子供という無防備かつ回復不能な存在に対して、性的な行為やトラウマを刻印することは、誰であれ、許されることではない。でなくても、児童ポルノは、「趣味の問題」として相対化できるカテゴリーではない。どこの国でも明々白々たる犯罪として当局の取り締まりの対象になっている。当然だ。
さて、それでは、絵に描いた児童を性的な対象とする作品を、我々はどう評価すべきなのだろう。
これが、今回の論点だ。
「別にオッケーなんじゃない? 被害者いないんだし」
「いいえ。問題は被害者の有無ではありません。児童を性的に扱うという趣味性のおぞましさそのものが問題なのです。絵であれCGであれ音声であれ、子供を性的な関心の対象とするということ自体が規制されなければ、問題は解決しません」
と、議論は、おおよそ二つの方向で闘わされている。
日経ビジネスオンライン読者の多くは、「規制」の側に重心を置いている、と、私は推察している。平均値としては
「規制は当然。ただ、表現の自由を抑圧しないように注意を払う必要がある」
ぐらいだろうか。
規制に原則反対である人でも、ブツを見せられると、規制派に転向する組はけっこういるはずだ。
そう。見たことの無い人がはじめて現物を見ると、あれはとてもキツい。目を疑う。っていうか、直視をはばかる。そういう描かれ方の代物になっている。全部がそうではないという人もあろうが、そういうものはない、と言い切る人はいまい。
だから、こういう物件を見せられた上で、
「こんなものが必要だと思いますか?」
と問われたら、たぶん、子を持つ親のうちの九割は、一も二も無く
「不要」
と答えるはずだ。
「不要であるのみならず有害かつ不快。よって、こんなものはただちに消去すべきです」
と、怒りをあらわにする向きも、少なくないはず。当然の反応だ。学齢期前に見える子供がマジな性行為を強要されている絵柄を見て、それでもなお利口ぶってリベラルな表情を浮かべているのは、やはり特殊な人間だ。
が、私の思うに、真の論点は、露骨な描写の漫画作品を見てどう思うかというところには無い。
というよりも、ここを論点にしてはいけないのだ。
間違いの元。ヒステリーの焦点。場が荒れるだけだ。
児童ポルノ作品が、多くの一般人にとって不快な存在であることは、これは、議論以前の問題で、見ればわかることだ。誰だってあんなものを学校の図書館に置きたいとは思わない。
が、それを規制するということになると、それはそれで厄介な問題が別枠で浮上する。現在、問題になっているのはそこだ。
規制に反対する人々は、規制の倫理的根拠に疑義を表明しているのではなくて、むしろ規制がもたらすであろう弊害について懸念している。ゴキブリを駆除するのにナパーム弾を使うのは、過剰反応ではないのか? と。ここのところを見誤ってはならない。
改定案への意見具申を行った、東京都知事の付属機関である「東京都青少年問題協議会」の専門部会の議事録(こちらから)を読むと、悪質な児童ポルノ作品を資料として机の上に展開しながら、委員の人々が、次第に冷静さを失っていく様子が目に浮かぶ。
ああいうものを見せられて、それらがネットや携帯電話などを介して小学生でもアクセス可能、という前提の中で話をしていれば、当然、議論は過激化する。
でも、現実社会でも同じことだが、「到達可能」であることと「あえて踏み込む」ことの間には、相当な距離があるものなのだ。
リアルな世界でも、小学生が歌舞伎町を訪問することは可能だし、バスの切符(パスモ?)を買えば新宿二丁目で降りることだってできる。が、だからといって、「歌舞伎町を浄化せよ」だとか「二丁目を焼き尽くせ」と言う人はいない。ん? 石原都知事が言ってた、と? では言い直す。よほどアタマがアレな人でない限り、青少年にとって有害だからみたいな理由で現実の町を消そうと考える人間はいない。
【5/13(火)まで・2カ月無料】お申し込みで…
- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題
- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題
- 日経ビジネス最新号13年分のバックナンバーが読み放題